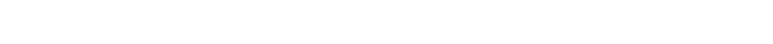2029年の開園100周年に向けて進化中の「熊本市動植物園」。2回に分けて園の魅力をお届けしているシリーズの前編では、愛くるしい動物がたくさん登場しました。
後編では、江津湖で暮らす魚や、身近な両生類・は虫類、日本で唯一観ることのできる動物など、屋内施設で観察できる動物をご紹介します。
意外と知らない身近な生き物にふれる「いきもの学習センター」

熊本市動植物園には、「いきもの学習センター」や「水辺のインフォメーションセンター」といった屋内で生き物を観察できる施設があります。
「いきもの学習センターは、以前は『動物資料館』という名前で展示を行っていました。暮らしに身近な両生類・は虫類、動物のはく製など、屋内でしか展示できないものについて学ぶことができ、さらに水辺のインフォメーションセンターには、江津湖で暮らす魚たちのアクアリウムもあるんです。天候に左右されず、多くの生物のことを知ることができる施設です」。そう教えてくれたのは、今回ご案内いただいた獣医師の飯冨順子さん(左)と藤井妙子さんです。

「学習」と名前がつくと、つい机の上で勉強する場所なのかな…と考えてしまいますが、動物園と植物園の中間に位置する「いきもの学習センター」では、楽しく学んでほしいという想いから、さまざまな工夫がされていました。
例えば、この水槽にはサンショウウオがいます。どこにいるでしょう?

水草や岩などに隠れて生息するサンショウウオは、見つけるのにひと苦労。子どもたちはそれを探すのに夢中になり、その経験が生き物たちの生態などを知るきっかけになるということです。
正解はこちら。飼育員さんたちも見失いそうなほど、上手に隠れていて、エサの時間になると顔を出すそうです。

イラストを用いたパネルも展示され、本物の生き物を観ながら学べる点もポイントです。

日本で唯一、動物園で展示している「ダマラランドデバネズミ」もいます。

モグラのように地下に生息するデバネズミを2種類観察することができ、右側は、一見、モルモットのような見た目の「ダマラランドデバネズミ」です。

左側にいるのは、デバネズミの中でも最小の「ハダカデバネズミ」で、その名の通り毛がなく裸んぼ!撮影時には、仲間がすみっこで固まっているにも関わらず、一匹だけトンネル内を行き来していました。

センターの奥には、園の歴史を知ることのできる展示もあり、戦時下の動物園のことや、これまで園で暮らしていた動物のはく製が並んでいます。

戦争によって起きたエサ不足や、猛獣やゾウの殺処分など……、人間の都合で命を奪われた動物たちのことは、忘れてはいけない記録です。
「いきもの学習センター」では、定期的に飼育員によるガイドも行われており、一番の人気は土・日・祝日に行われる「カブトムシ・クワガタムシのガイド」です。
実は、飼育員の松成忠広さんが、趣味で集めていたカブトムシ・クワガタムシをセンターに展示したところ大きな話題になり、今では約40種類!子どもだけでなく、大人も夢中になる人気コーナーになっています。



他にも、生き物に関する本を閲覧できる図書スペースや、連携機関の研究発表の展示など、ここだけでも何時間も過ごせそうです。
無料で見学できる「水辺のインフォメーションセンター」

「熊本市動植物園」には3つの入口があり、こちらは植物園側にある西門です。2022年3月に新設された「水辺のインフォメーションセンター」は、園の外にあり、入口は門の手前、左側にあります。
施設内は、江津湖の生態が分かる展示になっており、目玉の「江津湖アクアリウム」は、子どもたちにも大人気。それが、無料で見学できるのは驚きです!

江津湖の環境について学べる展示や多目的室のほか、アクアリウム(ミニ水族館)では江津湖で暮らす魚を観察することができます。

奥には、上江津湖・下江津湖を再現した水槽が並び、見比べることができ、湧水が多く水深の浅い上江津湖、水深の深い下江津湖の様子が一目瞭然です。

上江津の水槽をよく見ると、湧水がポコポコと湧いている様子が再現され、小魚が多いことが分かります。

一方、下江津は魚のサイズが大きく、種類も異なります。

「江津湖で暮らす魚は約30種類と言われ、同じ江津湖でも生息地によって湧水量の違いや水深の違いがあるため、暮らす魚も異なってくるんです」と飼育員の松成さん。カブトムシ・クワガタムシだけでなく、江津湖の魚にもとても詳しい飼育員さんです。
中でも注目なのが「タナゴ」です。日本に18種類いるタナゴのうち、江津湖にはなんと7種類も生息しているということで、これはとても珍しいことだといいます。





展示だけじゃない!体験して学ぶ「学習プログラム」って?

「動物園には、『種の保存』『教育・環境教育』『調査・研究』『レクリエーション』という4つの役割があります。正しい知識を深めてもらうことを目指し、学習プログラムを企画・実施しています。保育園や幼稚園、小・中・高等学校だけでなく、子ども会や教育関係団体の皆さんに活用していただいています」と飯冨さん。
学習プログラムは48のコースがあり、内容もさまざまです。
例えば、ゾウが長い鼻を使って食事をする様子を見学できる『24.ゾウの竹採食』を遠足の際に申し込んだり、地震時の動植物園の様子を知ることができる『4.熊本地震を乗り越えて』を修学旅行に組み込んだり。学びたいことやスケジュール、人数などによって、相談しながら組んでいくというものです。
動物が優先になるため、要望通りに予約が取れないこともあるので、まずは、事前に問い合せるのがおすすめです。

内容によっては事前予約が必要なく定期的に行われているガイドや、夏休みなどの長期休暇に開催されるワークショップなど、気軽に参加できるものもあるそうです。詳しくはホームページに掲載されるので、こまめにチェックしましょう。
長期休暇に行なわれるプログラムの中には、羊の毛を使った毛紡ぎ体験や、シカのツノでアクセサリーを作ったり、ゾウの糞でハガキを作ったりと、動物からもらったものを使ったワークショップが開催されます。

ワークショップを通して、有害鳥獣に指定されているシカがなぜ人里に出てこなければいけないのか?その原因を学んだり、ゾウの糞から食べているものや消化について知ることができたり。さまざまな動物の生態や、環境破壊などに意識を向けてほしいという狙いがあり、楽しく学ぶキッカケになると言います。
自然もいっぱい!散策しながら学べる植物園

西門から入った植物園側は、あちらこちらでピクニックができたり、水遊びができたりと、緑豊かなスペースが広がっています。

湧水が流れる小川では、「スイゼンジノリ」の保全活動が行われているので、江津湖に生育する植物のことを学ぶことができます。

また、「水辺のインフォメーションセンター」と同じ施設にある「緑の相談所」の先生が手がける「野菜花だん」には、水前寺菜やオクラ、大根、ネギなど、季節の野菜がたくさん茂っています。園内で野菜を育てながら、お客さんに向けて「野菜花だんガイド」も開催。夏はスイカなど、タイミングが合えばおすそ分けがもらえることも!家庭菜園の悩みなども、ぜひ相談してみてください。

2回に分けてご紹介した「熊本市動植物園」の魅力、いかがでしたでしょうか?
取材を通して感じたのは、スタッフの皆さんが本当に楽しく仕事をされているということ。飼育員さんによるガイドやワークショップなどをうまく活用しながら園を巡れば、今まで以上に、生き物や植物について知ることができ、考えることで、行動につながるかもしれません。
「熊本市動植物園」は、子どもはもちろん、大人になっても感動することばかり!
ゆっくりと時間を作って、ぜひ足を運んでみませんか。
■熊本市動植物園
所在地:熊本市東区健軍5-14-2
問い合わせ先:096-368-4416
営業時間:9:00〜17:00(夜間開園はHPで確認を)、「いきもの学習センター」「水辺のインフォメーションセンター」9:00〜16:30
休み:月曜(祝日の場合は翌日)
構成・取材・文・撮影/今村ゆきこ
同じテーマの記事
-

熊本の窯元をめぐる 熊本、うつわ便り 16 山下太さん
2024.10.16
-

熊本市電 電停ぶらり旅 A系統 [4]:祇園橋編
2024.07.24
-

新・熊本市動植物園のあるきかた[前編:愛らしい動物たちの姿に癒される]
2024.09.13