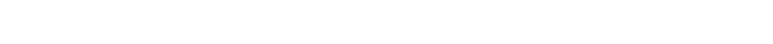熊本の窯元を巡り、そのつくり手をご紹介する「熊本、うつわ便り」。今回は天草市で作陶する 「器峰(きぼう)窯」の岡部俊郎さんをご紹介します。
天草陶石を使った透明感のある白い肌に、藍色の濃淡や筆致の強弱で表現する繊細かつ大胆な絵付け。一幅の水墨画のように味わい深 いこれらの焼き物は、岡部さんと妻の綾子さんによる共同作業でつくられています。
伝統ある窯元から独立 作り手として上を目指す
波穏やかな内海に面した天草市本渡町。澄んだ空がどこまでも続くように広がり、心なしか雲ものびのびとしているよう。「ここは、青と白の世界です」。岡部俊郎さんはそう天草の景色を表現します。

岡部さんは1974年、「水の平焼」の次男としてここで生まれ、育ちました。「水の平焼」は 1765年に岡部常兵衛さんが開窯した県内でも有数の歴史ある窯元です。複雑で深みのある色合いが特徴の海鼠釉(なまこゆう)の元祖としても知られており、現在は岡部さんの兄の岡部祐一さんが8代目として窯を受け継いでいます。

岡部さんは幼い頃から粘土遊びが好きな少年だったと言います。「自分の手で世界に一つだけの何かを作り出すことに面白さを感じていたのかな」と岡部さん。「剣道や書道などいろいろな習い事をさせてもらったけれど、全て途中で嫌になってやめてしまって(笑)。だけど粘土遊びに飽きることはありませんでした。幼稚園に通う頃には焼き物を仕事にしたいと思っていたような記憶があります」。その思いを実現させるべく、有田窯業大学校に進学。卒業後は長崎県波佐見町の中尾山伝習館でのインストラクターやフリーターを経て、2002年に帰郷しました。

その後は実家の「水の平焼」を手伝いながら、陶芸教室をスタート。「水の平焼」では磁土を、 教室では陶土を使って仕事をするうち、磁土で自分の作品を作りたいとの思いが強くなってきたと話します。「天草は世界でも最上級とされる陶石が採れる土地なのに、なぜか磁器の作家が少ない。天草陶石の白の美しさを伝える器を作ろうと思いました」。

そして2012年、帰郷して10年の節目に自身のブランドを立ち上げました。「水の平焼」の重油窯跡を作業場としたブランドの名前は「器峰窯」。染色家でもある知人から、「水の平焼という大きな山から独立するならその山を越えるくらいの気概がなければ。器の作り手として上を目指すという決意を込めて、屋号に〝峰〟の文字を使っては」と提案されたことにヒントを得て名付けたそうです。

失敗は成功のチャンス 次のためのヒントを探る
「器峰窯」の器は青と白をテーマに作られています。天草陶石を使った濁りのない白い肌に、 藍色の濃淡や筆致の強弱で表現する繊細かつ大胆な絵付けの器のほか、絵付けのない真っ白な器、瑠璃色一色の器もギャラリーに並んでいます。制作の際は、成形を岡部さん、絵付けは妻の 綾子さんと役割を分担。岡部さんは「妻も有田窯業大学校で学んだ経験があるので、お互いに形や絵付けのリクエストを出し合って二人三脚で作業しています」と教えてくれます。


器を作る上で大切にしていることを岡部さんに尋ねると、「使いやすさです」ときっぱり。年齢を重ねても手に取りやすい軽さ、日常的な使用に耐えうる強度、料理が映える形や絵付け...。 使う人の視点に立ってあれこれと思案しているそうです。

絵付けのモチーフは、古来から伝わる文様や図案を現代風にアレンジしたものや、海辺で拾った石の形状から着想した花などさまざま。愛猫をモデルにした作品もあります。


「器峰窯」の器をまず一つ求めるなら、蕎麦猪口がおすすめ。蝶を追いかける猫がモチーフのものは底に蝶がこっそりと描かれていたり、蛸が器いっぱいに描かれたものは脚がにょろにょろと内側まで伸びていたり...。ストーリーのある絵付けに魅了され、手に取ってあらゆる角度から眺めたくなります。めんつゆを入れるだけでなく、ちょっとしたおつまみを盛るのにも最適なサイズ。コレクションしたくなるラインナップです。


幼い頃から変わらず焼き物が好きな岡部さん。飽きたり嫌いになったりすることは今後もきっとないけれど、難しいと感じることはあるそうです。「だけど、失敗は成功のチャンス。失敗の中に次のためのヒントが必ずあるので、それを見逃さずに次に生かすことが大切」とも。今後は 実家の蔵で眠っていた「水の平焼」5代目の岡部源四郎が遺した画集に光を当て、創作のヒントにすることも考えていると言います。

「流行を追い始めたら二番煎じから抜け出せない。好きを掘り下げれば第一人者になれるかもしれない。僕は、後者でありたいと思います」。〝好き〟を原動力に焼き物と向き合い続ける岡部さん。そのまっすぐな姿勢が、天草の海の水平線と重なって見えました。

■器峰窯
場所:熊本県天草市本渡町本戸馬場2004
インスタグラム : @okabetoshio
■展示会情報
涼を楽しむ器展
開催日時:2024年8月8日(木)~12日(月・祝)、10:00~17:00
※入館は~16:00
場所:島田美術館ギャラリー(熊本県熊本市西区島崎4-5-28)
問い合わせ先:096-352-4597(島田美術館)
(取材・文・撮影/三星 舞)
同じテーマの記事
-

熊本市電 電停ぶらり旅 B系統 [3]:本妙寺入口編
2022.12.20
-

熊本の窯元をめぐる 熊本、うつわ便り 11 高田焼 上野窯
2023.10.13
-

熊本、うつわ便り 04 江浦久志さん
2021.08.31