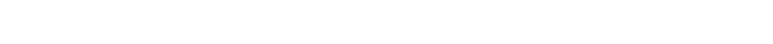熊本の窯元を巡り、そのつくり手をご紹介する「熊本、うつわ便り」。熊本県伝統工芸館の学芸員・池田昌一郎さんに熊本の伝統的な焼きものについて教えていただいた前回から続いて、県内で古くから続いている窯元を訪ねていきます。
まずは、400年の歴史を持つ高田焼(八代焼)の窯元・上野(あがの)窯へ。現存する高田焼の窯元、上野窯、竜元窯(りゅうげんがま)、伝七窯(でんしちがま)のうち、上野窯は開祖・尊楷(そんかい)から直系で続く高田焼の宗家です。現在は12代当主の上野浩之さんと13代目の上野浩平さんが親子で窯を守っています。
細川家と歩んだ江戸時代 明治維新後に宗家のみに
八代市日奈久町。俳人の種田山頭火が〝一生動きたくないのだが〟と詠った日奈久温泉のほど近くにある高田焼上野窯。高田焼の始まりは、江戸時代と伝わります。


豊前(現在の福岡)小倉藩主だった細川忠興が、朝鮮の陶工・尊楷(そんかい、後に上野喜蔵と改名)の作品を気に入って召し抱え、1602年に自身が治める上野(あがの、現在の田川郡福智町)に築窯。忠興はその後、1632年に細川家が領地移転で肥後へ入国する際にも尊楷をともない、自らが暮らす八代に新たに窯を築かせ、肥後藩の御用窯として保護してきました。
尊楷が89歳でこの世を去った後は、息子の上野忠兵衛と徳兵衛が窯を守っていましたが、明治維新後に藩の保護が廃止。徳兵衛とその息子の百柴を祖とする分家二家は廃窯し、宗家の上野窯のみとなりました。

現在、上野窯の当主は12代目の上野浩之さんが務めています。「御用窯の性格上、藩主が変わるごとに様式が少しずつ変化してきました」と浩之さん。上野窯の特徴とされる青磁象嵌は、3代目・忠兵衛の時代に始まったとされています。象嵌は、半乾きの素地に竹べらなどで文様を彫り、へこみに長石を埋め込む難度の高い技法です。


当初は素朴で単純な文様を彫っていましたが、江戸末期には花鳥風月をリアルに表現する〝描くように彫る〟様式に変化。いっそう高度な技術が必要とされるようになり、手間もかかるため、限られた造り手のみが生産できたと伝わります。浩之さんは、「当時の細川家は、品性の高い焼き物がごく少量あれば良いとの考え方から大量生産を好まず、積極的に窯を増やそうとはしなかったようです。そのため、美濃焼や伊万里焼のように産地として発展することがなかったのでは」と話します。

苦労を忍んだ先祖のありがたさ 〝変化する〟真の伝統工芸を追求
分家二家の廃窯後も火を絶やすことなく続く上野窯。浩之さんは「しかし、決して楽ではなかったはずです」と当時を推察します。御用窯時代は、器の形や象嵌の文様を細かく指示する「指図(さしず)書」とともに、土や薪などが藩から届けられていました。ところが藩の保護がなくなり、さらに日清戦争や日露戦争と戦争の時代に突入。「特に7代目から10代目は器どころではない状況の中でも、窯を閉じることなく耐えてくれた。苦労を忍んでくれた先祖のありがたさを感じずにはいられません」。

浩之さんは11代目・才助さんの長男として生まれました。「姉が三人で、男子は私のみ。窯を継ぐ以外の選択肢を考えたこともなく、自然とこの道に進みました」。浩之さんは才助さんの作陶の様子をひたすら見つめ、手を動かすことで、技を身につけてきたと話します。「父は口数が少なく、口頭で何かを教えてくれるような人ではありませんでした。でも、その存在が心強かった。初めは父の模倣でしたが、次第に自分を器に投影できるようになってきました」。


代々つないできた技法を守る一方で、「同じことをするのは真の伝統工芸とは言えない」と浩之さんはきっぱり。「67歳になった今、やっとそれが分かるようになりました。とはいえ、私はまだ先人たちの足元にたどり着いたばかり。陶芸のなんと奥深いことか。古いことも新しいことも、まだまだ学ばなければいけない立場にいます」と相好を崩します。


金工との共通点を見出し陶芸の道へ 土だけで千変万化の色を追求する
一方、浩之さんの息子で13代目の浩平さんは、「土に興味がなく、ろくろに触ったこともありませんでした」と幼少期を振り返ります。宗家の長男として生まれ、後継者としての視線を「うすうす感じていた」ものの、東京藝術大学では彫金を専攻。創作に没頭するうち、金属を土と相対的に考えている自分にふと気づいたと言います。「例えば、金属を融合させる合金は、土をブレンドして作る青磁に似ている。派手な色を使わずに土そのものの色の美しさを生かす高田焼の特徴も、金工とよく似ている。このことに気付いてから、土に魅力を感じるようになりました」。

大学を卒業後は京都で1年間陶芸の基礎を学び、帰郷してからは浩之さんに師事。大学で陶芸を専攻した人と自身を比較し、「出遅れている」と焦る気持ちがあったといいます。「アイデアはあるのに、手が追いつかないジレンマがありました」。

創作の方向性が見え始めたのは2016年頃。「倹約家で知られる徳川吉宗の時代、華美が良しとされない風潮の中で庶民が茶系や灰色のみで〝四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねず)〟といわれるほど多様な色の変化を生み出したことにヒントを得て、釉薬に頼らずに土だけで千変万化の色を出せるのではと気付いたのです」。そこから、階調の異なる土を段階的に変えながら埋め込み、グラデーションを表現する独自の技法「霞鼠(かすみねず)」を生み出しました。

業者から購入した土で作陶するのが主流の現代では珍しく、上野窯の器づくりは土の掘削から始まります。親子で日奈久の山の土を堀り、採った土を粉砕し、ふるいにかけて木の根や葉を取り除いて、水に溶かし、濾し…。数々の工程を経て、象嵌に適したきめの細かい土を作ります。そこから土を練り、成形し、半乾きに乾かし、そこから象嵌作業へ。前述の通り、素地に竹べらなどで模様を彫り、へこみに長石を埋めて乾かし、余分な長石を削り落として、素焼き。自然に冷ましたら釉薬をかけ、ようやく最終工程の本焼きへ。完成までにかかる時間は柄の多さや素地のサイズによって異なりますが、基本は削りに3~4日、埋め込みにさらに3~4日かかるといいます。

青磁象嵌はただでさえ難易度が高く、手数の多い技法です。「霞鼠は、さらに面倒なことをやっている。同業者に工程を説明すると、ドン引きされることもあります」と浩平さんは苦笑い。陶器は焼くと縮まり、その収縮率は土ごとに異なるため、完成までの間に割れやゆがみが出てしまう危険性をはらんでいます。「それでも、挑み続けたい。藩の指示通りにしか焼けなかった御用窯時代とは違って、今は自由に創作ができるのだから」。

400年の歴史の重みを感じながら 父と子で肩を並べ土と向かい合う
浩平さんは「土に触れるようになり15年ほどたった今、脳内のイメージに手が追いついてきました」と言います。日本人ならではの繊細で豊かな感性を生かす新しい技法を追究するだけでなく、料理人や茶師など異業種とコラボレーションしてオリジナルの陶器を作るなどの試みにも積極的に取り組んでいます。それでも、「変えてはいけない境界線」には慎重です。「高田焼は、産地にならなかった分、受け継いでいるものの純度が高いのではないかと思っています。先祖の作品を見ると、藩からの指図通りに作っているにも関わらず代ごとに個性が感じられたり、変えてはいけない境界線を必死で探った形跡が見て取れたりする。私も〝高田焼らしさ〟を見間違えることなく、その中で何かを残していきたい」。

上野窯の焼きものの愛好家の中には、代々の作品を蒐集している方も少なくありません。「祖父や父、さらにその前の先人たちの焼きものと並べられると思うと、背筋が伸びます。作り手よりも、作品の方がずっと寿命が長い。怖いことです」と浩平さん。浩之さんは「お客さまから作風に関する忠告をいただくこともありますが、それはつまり、伸びしろを与えていただいたということ。息子の浩平にも、いろいろなことにチャレンジしてほしいと願っています」と胸のうちを話します。


一子相伝で脈々と続いてきた高田焼上野窯。「土味(つちあじ)と技法を壊すことなく、時代ごとの作り手の個性を活かして、ゆたかに表現していきたいと思っています」と語る父親に続いて、浩平さんは「個人の作家が増えた今、ライバルは多いし、使い手の目も厳しい。おまけに、400年の歴史はどうにも重たい」とひと息。「でも、今日も土を触っている自分がいる。焼きものを好きになっちゃったんだから、仕方ないですね(笑)。作品からは歴史の重さや足掻きが滲まないような仕事をしたい」。上野窯の作業場には、肩を並べて土と対峙する父と子の姿がありました。

■高田焼宗家 上野窯
住所:熊本県八代市日奈久東町174
問合せ先: 0965-38-0416
インスタグラム:@aganogama
■展示会情報
高田焼宗家 上野窯
上野浩之・浩平 作陶展
開催日時:2023年10月18日(水)~24日(火)10時~19時
※最終日の10月24日(火)は16時閉場
場所:鶴屋百貨店 本館8階美術ギャラリー(熊本県熊本市中央区手取本町6-1 8F)
問い合わせ先:096-327-3664(本館8階美術ギャラリー)
(取材・文・撮影/三星 舞)
同じテーマの記事
-

世界で活躍する竹あかり演出集団C H I K A K E Nが手がける! 「かぐや姫の光る庭 in サクラマチクマモト」開催中
2025.03.19
-

熊本市電 電停ぶらり旅 A系統[2]:二本木口編
2022.06.08
-

シェアサイクルサービス・チャリチャリを初体験!【ベーシック編】
2023.11.09