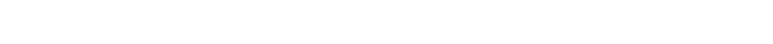おいしいもの、美しい景色、貴重な体験……旅を豊かにするものはたくさんありますが、
地元の人と交わした何気ない会話や一期一会が色濃く印象に残ったりするものです。
熊本城のふもとに位置する観光施設「桜の馬場 城彩苑」。
敷地内の「桜の小路」には、熊本の特産品を吟味できる23店舗が軒を連ねています。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、延期されていた熊本城特別見学通路が
6月に公開となり、新たな角度から熊本城復興の様子を眺めることができるようになりました。
今回は、城彩苑のお店から、3人の名物店主とオススメの品をご紹介。
ふと時間ができたとき、お土産に迷ったときなど、お気軽にお立ち寄りください。
きっと、旅のワンシーンを彩る楽しい出会いがありますよ。
1. 女将の熊本弁、高菜漬けの味比べを堪能! 「阿蘇たかな漬本舗 菊屋」

「とりあえず、食べてみなさらんね」
着物姿で試食を勧めてくれるのは、女将の栗崎真須美さん。
ここ菊屋は、阿蘇外輪山でしか育たない高山植物「阿蘇高菜」の専門店。
福岡を中心に九州各地で高菜は栽培されていますが、それは三池高菜という品種。
阿蘇の山上で寒い冬を越した阿蘇高菜は、ピリッとした辛さが特徴です。

小さなお子さまも食べられる『油炒め』も人気。
温かいご飯に混ぜて高菜飯として楽しめる『からし高菜』は、油不使用のため冷えても美味です。
封を開けてそのまま食べられる手軽さが、若い人を中心に支持を得ているそう。

伝統ある「阿蘇たかな」を味わいたいという方は、この一本漬けをどうぞ。
半年漬け込んだ古漬けは、塩分が少なく酸味が強いツウの味です。

菊屋に並ぶ種類豊富な商品のすべてが試食可能。
これは栗崎さんのこだわりです。
「全部オリジナルだから、食べてみないとわからないでしょう?
“おいしくなかったら買わんでいいけんね!ここでしか食べられんとだけん、食べていきなっせ! ”
と試食を勧めています。食べていただくことが、熊本の文化を知っていただくことになる。
熊本でこういうものを食べたという記憶を頭の隅にでも置いてもらえることが、私の目的なんです」

オープン当初からずっと城彩苑で働く栗崎さんは、お客様に対して特別な思いがあるそう。
「2016年の熊本地震後、お城が崩れてしまったので観光のお客様はぐんと減りました。
でも、ボランティアの方や応援の気持ちで訪れてくださる方が多く見えるようになったんです。
震災当時の様子をお話しすると、頑張ってるね、また来るからねと温かいお言葉をいただくので、
“20年先はおらんかもしれんばってん、ここ1、2年はおるけんまた来てくださいね”とお伝えしています」
〈店主ピックアップ〉“これも食べてみて!”
『高菜のしぐれ』

菊屋人気No.1の商品です。
きくらげ、魚卵、こんにゃく、シソの実と高菜を混ぜこんだ一品。
青いうちに収穫した阿蘇の三池高菜を使用しています。
箸が止まらなくなるご飯のおかずは、日持ちが1年とお土産にも最適です。
ぜひ、炊きたてのご飯と一緒に召し上がってください。
【阿蘇たかな漬本舗 菊屋】
電話:096-356-5525
2.お茶のおいしさと魅力を再発見! 「お茶の泉園」

軽快なトークとお茶の香りで、道ゆく人たちの足を止めるのは、店主の谷口裕一さん。
見事な手捌きで淹れたおいしいお茶を、次々に配っています。
泉園の茶畑があるのは、その昔、平家が集落をつくったと言われる八代市泉町・五家荘。
山に囲まれた霧深い地で日中の寒暖差が大きく、そこで育ったお茶は香りが出るそう。
香り高い味を、まずは試飲で確かめてみてください。

プロが淹れたお茶は、紙コップということを忘れるような本格的な味。
まろやかな甘みと程よい苦味を出す、おいしい淹れ方も教えてもらえます。

一番人気の『いずみ茶・香』は、泉園の看板商品。
お茶の良さが見直されていることもあり、年代を問わずお買い求めになる方が増えているようです。

急須を使わずに気軽に緑茶を楽しめる、いずみ茶(緑茶)と、ほうじ茶、玄米茶のティーバッグタイプもあります。お土産に良さそうです。

『食べる緑茶』は、一番茶をパウダー状にした贅沢な緑茶。
臼で引いているため粒子は細かく、さっと水やお湯に溶けます。
その品質の高さとおいしさに、リピーターが続出しているのだとか。
塩に混ぜて「緑茶塩」にしたり、お料理・お菓子に使ったりとアレンジの幅も広がります。
「現代においてもお茶が日常生活の一部になるように、ティーバッグやパウダーといった形態を変えた商品を開発しました。
急須を使って飲まなくても、時代に合わせて形が変わっても、ティーバッグの玄米茶に相場より良い緑茶を使ったり、
パウダーに一番茶を使用したりとお茶の品質にはこだわり続けています」

店頭に並ぶお茶7種類は、すべて同じ価格。
それは、値段ではなく好みで選んでもらいたいという思いから。

「うちは、販売というよりお客様との会話を楽しむことがベースです。
実際にお家でお茶を飲んでくださることが一番嬉しいので、
お茶の良さをお伝えしながら、お客様の好みやライフスタイルにあった商品を提案しています。
お客様との思いがけない出会いがあるのもこの仕事の醍醐味。
たとえばデザイナーさんだというお客様からいただいた助言を元に、パッケージを変えたことがあります。
こんな出会いを楽しみながら、毎日お客様をお迎えしています」
〈店主ピックアップ〉“これも食べてみて!”
『お茶の香りソフト あずき添え』

充実のテイクアウトメニューは、本物のお茶を気軽に楽しんでほしいという思いを持つ泉園ならでは。
一番人気は、食べる緑茶をたっぷり練りこんだソフトクリーム『お茶の香りソフト』。
抹茶とは一味ちがう独特の風味を楽しめます。
このほか、『ほうじ茶ソフト』やラテ、ぜんざいなども人気です。
【お茶の泉園】
電話:096-288-0015
3.一口食べればわかる、女将自慢の逸品! 「五山房 壱の蔵」

オリジナル商品『赤酒めんたい』をつくるために創業されたという五山房 壱の蔵。
女将の田代京子さんは、社内でも赤酒めんたいを知り尽くす存在だそう。
五山房の辛子明太子は、赤酒で120時間熟成させてつくられます。
赤酒とは、強い甘みが特徴の肥後細川藩のお国酒で、
現在では全国の料亭でみりん代わりに使われることがあり、
「当店では赤酒を使用しています」と掲示されるお店を見かけることがあります。
熊本では、お正月のお屠蘇といえば赤酒。
家庭の煮物などにも赤酒が使われるほど、馴染み深いお酒なのです。

「みりんやお酒は酸性ですが、赤酒は弱アルカリ性。
アルコールを省けば人間の体液に一番近いpHなんです。
だから体に浸透するし、化学調味料を多く使わなくてもおいしくなる。
口の中に残らないさらっとした旨味こそ、赤酒めんたいの特徴なんです」

熊本の「水・酒・塩・醤油・唐辛子」と赤酒でつくられる明太子は、素材も厳選。
すけそう鱈の卵も、基本的に北海道で採れた国産のものを使用しています。
キメの細かさ、粒立ちなど、外国産との違いは確か。
上質な辛子明太子として、著名人のファンやリピーターも多いのだといいます。

赤酒仕込みのめんたいを丸ごと焼き上げた『焼きめんたい』も人気。
お弁当のおかずやおにぎりの具にもオススメです。

試食を勧めながら、熱くめんたいを語る田代さん。
「私は、商品を好きにならないと売れない性格なんです。
今こうして赤酒めんたいを売れるのは、本当に好きで、自信があるから。
赤酒めんたいのことなら熟知していると自負していますが、魚も卵も自然のもの。
奥深いのでわからないことは社長に聞きますし、未だに勉強は欠かせません。
他の社員に説明の指導をする際も、熱が入って厳しくなってしまいます(笑)。
決してお安いものではないですが、食べてもらえればそのおいしさは分かっていただけるはず。
商品に自信があるから、お客様にその良さをちゃんと伝えていきたいんです」
〈店主ピックアップ〉“これも食べてみて!”
『ゆずの実あさり』

五山房 壱の蔵は、佃煮も珍味もちろん赤酒仕込み。
その中でも『ゆずあさり』は、特に人気の商品です。
甘みとゆずの香り、遅れて明太の辛味が感じられる、味のバランスが絶妙な一品。
ご飯のお供はもちろん、お酒のアテにもぴったりです。
【五山房 壱の蔵】
電話:096-325-7530

「熊本高菜の味を堪能するのなら『おにぎり高菜』がオススメ。
大きな葉のままのお漬物は、おにぎりにぐるっと巻いて食べられます。
同じテーマの記事
-

九州初!熊本初!新業態!が続々。「アミュプラザくまもと」に潜入取材!
2021.05.07
-

3年ぶり、あの感動を再び! ランナーも沿道も沸く熊本城マラソンものがたり~応援ボランティア編~
2023.02.15
-

空中回廊から 熊本城のいまvol.3
2020.05.08